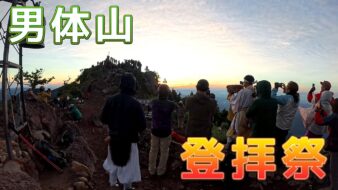この記事はプロモーションが含まれています
男体山登拝祭でご来光を拝むための6つの攻略ポイント!(夜間登山)

男体山登拝祭の攻略のコツをお伝えします。
登拝祭は、毎年夏に行われる神聖な登山祭りで、深夜から山頂を目指し、ご来光を拝むイベントです。地元の文化や歴史に根ざした特別な行事となっています。
今回は、男体山登拝のための攻略のコツをお伝えします。この記事を読めば、初めて参加するひとでも安心して登山ができるはずです。ぜひ参考にしてください。
男体山登拝祭とは?
まずは、「男体山」と「登拝祭」について、それぞれ解説します。
登拝祭の様子は、上記の動画をぜひご覧ください。
男体山とは

男体山は日本百名山のひとつで、標高2,486mほどあります。栃木を象徴する山ともいわれ、見た目や風格はとても良い山ですね。
男体山を一言でいうと、「かなりきつい山」になります。標高差は1200mあるので、上級者向けです。
 やますぐ
やますぐ独立峰なので頂上は絶景!
なぜきついのか?
男体山がきついといわれるのには、理由があります。
男体山がきつい3つの理由
- 標高差が約1200mある
- ほぼ直登なので傾斜がきつい
- 岩場も長い
特に二つ目が問題で、3-4合目の車道歩き以外はずっと直登になります。
そのため、かなり筋力が必要な山です。この山は、体力以上に筋力が重要ですね。
登拝祭とは
そんな男体山を、夜中にのぼってご来光を拝むのが「登拝祭」です。
深夜0時からスタートし、頂上でご来光を拝みます。二荒山神社ではその間もお祭りがやっており、深山踊りや花火を見ることができます。
登山開始は0時ですが、結構長くお祭りはやっているので、時間は潰しやすいかとおもいます。終始賑やかですね。
登拝祭の期間
登拝祭の日程は、以下の通りです。
夜間登山=8月1日と8月4日の午前0時
ご来光を拝むイベントなので、午前0時スタートです。
日付が変わるので、厳密には「7月31日の夜」と「8月3日の夜」に、現地に向かうことになります。お間違いなきよう。
登拝祭自体は、「7月31日~8月7日の8日間」ありますが、夜間登山は2日間だけなので注意しましょう。当日の夜に登山受付しています。(入山料1000円必要)
上記は2024年の日程です。日にちは毎年変わるかもしれないので、下記の二荒山神社のホームページでチェックしてみてください。
男体山登拝祭の事前準備
登拝祭は、深夜0時からのぼるため、事前の準備が大切です。
特に、「ヘッドライト」と「防寒具」は重要になります。
ヘッドライト
夜間登山なので、ヘッドライトは必須です。
ここでは、私が使った2つのヘッドライトをご紹介します。
ペツル アクティック


ヘッドライトといえば、やはりペツル。
スペックはMAX450ルーメンで、足元を均等に照らしてくれるのは、さすがペツルといったところ。
名のあるメーカーなので、ひとつ持っておくと良いでしょう。私は常に持ち歩いており、登拝祭でも活躍しました。
中国製の謎ヘッドライト


こっちのヘッドライトは、友人に貸し出しました。
168ルーメンのはずが、なぜか異様に明るく、5~6人分くらいまで照らしていました。ただ、買ったのはもう6年ほど前なので、今は売っていませんでした。
Amazonで売っている中国製のヘッドライトでも、十分登山で使えます。ただし、故障したりするときのことも考えて、ヘッドライトは常に2つ以上持っておくほうが無難ですね。
防寒具
早朝の山頂は非常に寒いので、防寒具は必須になります。
風を防ぐためのハードシェル(ウィンドブレーカー)や、手袋を用意しましょう。特に、早く着いた場合は、山頂で長い時間待つことになるため、身体が冷えやすいです。
私は防寒具は持っていったものの、全然寒くて終始ガクガクに震えていました。
マイクロパフフーディを持っていくか悩んだんですが、持っていけばよかったです。真冬並みの寒さでした。
男体山登拝祭の6つの攻略ポイント
ここでは、男体山登拝祭の攻略のポイントをお伝えします。
登拝祭攻略のポイント
- ご来光は剣の方向にでる
- 事前に一度はのぼろう
- トレーニングはしておくこと
- ご飯はしっかり
- 防寒対策もしっかり
- 7合目の岩場
ご来光は剣の方向


ご来光は、剣のある方向にでます。
剣のあるあたりに位置どるか、少し離れた場所からだと見やすいです。ご来光の時間は、だいたい4時40分頃になります。
事前に一度はのぼろう
事前に一度はのぼっておきましょう。
男体山はきつい山です。しかも、深夜にのぼります。
登山者はたくさんいるので、道に迷うことはないでしょうが、どのくらい大変な山かは事前に知っておくべきです。
眠気と疲れで足元はフラつきやすいので、一度登ってどのポイントを気を付けるかしっかりと見極めておきましょう。
トレーニングはしておく
トレーニングもしておきましょう。
男体山は、筋力が必要な山です。足腰が弱いと、下山でバランスを崩しやすくなります。
実際に、私は男体山で滑落したひとを、目の前で見たことがあります。
男体山の登山者を見ると、ギリギリでのぼっているひとをよく見かけます。何度も言いますが、男体山はきつい山です。ギリギリでは危険です。
余裕をもってのぼれるように、スクワットやカーフレイズなどのトレーニングは必ずやっておきましょう。
ご飯はたくさん食べておく
ご飯は、事前にたくさん食べておきましょう。
男体山登山はかなりのカロリーを消費するため、いつも以上に食べておく必要があります。また、これは深夜ならではですが、夜中に行動食を食べるのはきついです。
考えてみてください。深夜にチョコレートを食べたいとおもいますか?
私はおなかが減ったのでチョコやお菓子を食べましたが、色々ときつかったです。後半はほぼ食べませんでしたね。
空腹はあっても、気持ち悪さが勝りやすいため、登山前に大量のカロリーを摂取しておいたほうが無難です。
防寒対策はしっかり
頂上は、真冬並みの寒さです。
防寒具や手袋などはしっかりと用意しておきましょう。私がのぼったときは、山頂で10度前後でした。
風はなかったので良かったですが、あれば相当寒かったとおもいます。日が出てくると段々と温かくはなりますが、ご来光の待機時間は身体も冷えるので注意が必要です。
ダウンやフリースはあったほうが良いですね。折りたたんで小さくできる、マイクロパフフーディはおすすめです。
7合目の岩場は要注意
男体山は、7合目あたりから長い岩場になります。
ここは男体山でもっとも核心部で、多くのひとが苦労するポイントです。また、登山中は眠気もあって、足元がフラつきやすく、普段よりも注意が必要です。
ゆっくりとのぼってもご来光には間に合いますので、焦らずに行きましょう。
男体山登拝祭におすすめの駐車場
男体山登拝祭におすすめの駐車場をご紹介します。
普段は「二荒山神社の境内」にとめられますが、お祭り中はとめることができないため、近くの駐車場にとめましょう。
ちなみに、入山受付をするときに、下記の駐車場の無料券がもらえました。なので、参加者はタダになります。
県営湖畔第一駐車場
登拝祭のときは、この駐車場にとめましょう。
229台収容可能で、トイレもあります。24時間営業なので、夜中でも明るいです。登山口である二荒山神社の近くにあります。
県営湖畔第二駐車場
第一駐車場が満車のときは、こちらにとめましょう。
58台収容可能。こちらも登山口までは近いです。
男体山登拝祭のよくある質問
男体山登拝祭に関するよくある質問をまとめました。
- 男体山の登拝祭とは何ですか?
-
男体山の登拝祭は、毎年夏に行われる神聖な登山祭りで、深夜から山頂を目指し、ご来光を拝むイベントです。地元の文化や歴史に根ざした特別な行事です。
- 登拝祭の参加には事前予約が必要ですか?
-
当日夜から現地で受付をしています。入山料1000円(2024年時点)が必要です。
- 登拝祭に必要な持ち物は何ですか?
-
普段の登山装備に加え、ヘッドライトと防寒具が必要です。山頂は、真冬並みに寒いので注意しましょう。
- ご来光は何時に見られますか?
-
ご来光は、だいたい4時40分頃に見られます。剣のある方向から拝むことができます。
- 緊急時の対応はどうすれば良いですか?
-
途中で救護所や自衛隊の方に助けを求めることができます。4合目や7.5合目、頂上などそれぞれの場所に設置されています。
- ひとりでものぼれますか?
-
ひとりでのぼっているひともいますし、私も当初はひとりでのぼる予定でした。
- 女性ひとりでも大丈夫ですか?
-
女性のソロ登山者も何人か見かけました。終始ひとの流れはありますので、ご安心ください。
- 山頂での防寒対策はどうすれば良いですか?
-
山頂は真冬並みの寒さです。ハードシェル(ウィンドブレーカー)や手袋や、帽子などがあると良いです。男体山は独立峰で風が強い場合があるため、風を通さない衣服は必須です。
- 登山前の準備で注意すべき点は何ですか?
-
十分な睡眠を取り、体調を整えておくことが重要です。また、事前のトレーニングは必ずしておきましょう。
- 登山中に気をつけるべきポイントは何ですか?
-
自分のペースで無理せず登ることが大切です。速くのぼることよりも、安全にのぼることを意識しましょう。
- トイレはありますが?
-
普段はありませんが、登拝祭では4合目に仮設トイレが設置してあります。
しっかりと準備していこう
この記事では、男体山登拝祭について解説しました。
男体山はきつい山なので、必ず事前に一度登って、トレーニングもしておきましょう。
安全面においては至れり尽くせりとなっているので、楽しめる登山イベントではないかとおもます。しっかりと準備して、ぜひ楽しんで行ってください。