この記事はプロモーションが含まれています
【これで完璧】阿蘇山高岳の初心者向けおすすめ登山ルートと規制情報

阿蘇山の登山ルートを詳しく解説します。
阿蘇山の最高峰は「高岳」です。頂上までは2つのルートがあり、噴火警戒レベル2までなら登山することが可能になっています。
この記事では、高岳までの登山地図、難易度、所要時間など、阿蘇山登山に必要な情報をすべてお伝えします。実際に私がのぼったレポートもありますので、登山を計画されているかたはご活用ください。
この記事を読めば、阿蘇山の登山がすべてわかるはずです。ぜひ参考にしてください。
\ ルート名をタップまたはクリックでジャンプ /
| 登山ルート概要 | ||
| 砂千里ルート | 中級レベル | 特徴 阿蘇山の火口側からのぼるルート。道中の噴火口は必見。はじめてのぼるならまずはここ。 |
| 仙酔峡ルート | 中級レベル | 特徴 最高峰である高岳を真っすぐ目指すルート。最短で頂上まで行きたいならここ。 |
 やますぐ
やますぐ阿蘇山登山の魅力をたっぷりとお伝えします!
阿蘇山の登山概要


| 名称 | 阿蘇山(あそさん) |
| 標高 | 1,592m |
| ジャンル | 日本百名山 |
| 登山エリア | 九州 |
| 都道府県 | 熊本県 |
| 登山適期 | 5月上旬~10月下旬 |
| 難易度 | 初級~中級 |
| 登山口と駐車場 | 阿蘇山の登山口と駐車場 |
阿蘇山は複数の山々の総称であり、最高峰は「高岳」になります。
高岳までは2つのルートがあり、これらは噴火警戒レベルが2までなら、のぼることができます。レベル3になると、どちらも登山禁止です。


そのため、登山前は必ず、噴火警戒レベルをチェックしておきましょう。
阿蘇山のおすすめ登山ルート


ここでは、阿蘇山の高岳までのルートをご紹介します。
| 登山ルート詳細 | ||||
| 砂千里ルート 中級レベル | 累計標高差 約730m | 往復距離 約9.6km | 登山時間 5時間30分 | 特徴 阿蘇山の火口側からのぼるルート。道中の噴火口は必見。はじめてのぼるならまずはここ。 |
| 仙酔峡ルート 中級レベル | 累計標高差 約780m | 往復距離 約5.6km | 登山時間 4時間30分 | 特徴 最高峰である高岳を真っすぐ目指すルート。最短で頂上まで行きたいならここ。 特徴 |


砂千里ルート


砂千里ヶ浜側から高岳を目指すルートです。



初めてならココがおすすめ!
このルートは歩く距離が長いんですが、道中に阿蘇山の火口を拝むことができます。噴火口までは車で行くこともできるため、観光&登山向けのルートです。
| 合計距離 | 9.58km |
| 最高点の標高 | 1,588m |
| 最低点の標高 | 1,135m |
| 累積標高(上り) | 727m |
| 累積標高(下り) | 727m |
一部急登を除けば、全体通してなめらかな登山道ですので、初心者でも比較的簡単にのぼれるはずです。
頂上までは、「仙酔峡ルート」のほうが近いですが、阿蘇山を初めてのぼるのであれば、第一火口が間近で見られるこのルートがおすすめ。
ただし、噴煙の出ている第一火口が見られるのは、噴火警戒レベル1のときだけです。
そのため、上記の地図と動画は、噴火警戒レベル2でも行ける「皿山迂回ルート」にしてあります。このルート通りなら、レベル2でも大丈夫です。
レベル1で第一火口まで行くときは、道路沿いに遊歩道があるので、すぐにわかるはずです。※青ルート部分
皿山を迂回すると火口からは離れてしまうので、もしレベル2になったら、仙酔峡ルートでもいいかもしれませんね。
なお、このルートは実際の登山レポートがありますので、下記を参照にしてください。
仙酔峡ルート
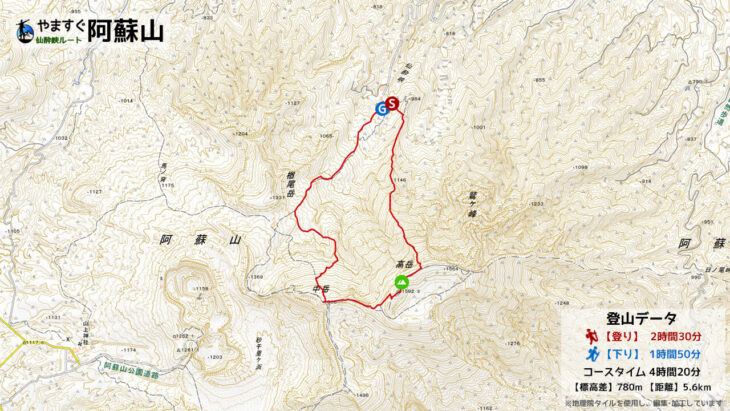
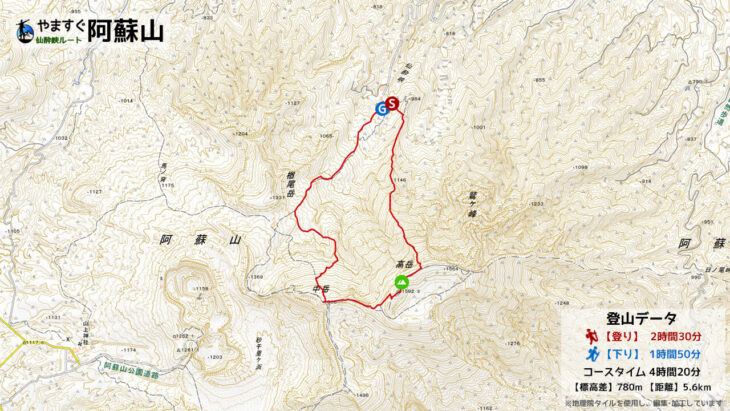
仙酔峡ルートは、高岳を真っ先に目指すルートです。
阿蘇山の最高峰である「高岳」を目指すだけであれば、こちらがおすすめになります。こっちは完全に登山者向けのルートで、結構急な登りです。
| 合計距離 | 5.61km |
| 最高点の標高 | 1,597m |
| 最低点の標高 | 912m |
| 累積標高(上り) | 784m |
| 累積標高(下り) | 784m |
阿蘇山登山の様子
実際に、「砂千里ルート」でのぼってきましたので、レポートします。
阿蘇山第一火口


まずは、第一火口を見に行きました。
阿蘇山の噴火口は、間近で見ることができます。ここまでは車で来ることができ(一部有料)、観光客も多く訪れています。
火口が目的なら、むしろここがピークです。
山頂を目的とした登山は、むしろ火口から離れていきます。
噴火が怖いというひとでも、ここに近づかずに登山することができるので、阿蘇山は案外のぼりやすいんじゃないでしょうか。
なかなか生きている火口に、ここまで近づくことはできないので、貴重な体験をさせてもらいました。



めっちゃ深かった
高岳は遠い


火口の向こう側にあるのが、中岳と高岳です。
砂千里ルートは、「火口をグルッと避けつつ頂上を目指すルート」なので、かなり距離があります。ただし、景色は火山として一級品なので、退屈はしませんでした。
火山らしいザレ場を体験しながら、ゆっくりと楽しんで登山ができます。
のぼりの核心部


木道が終わると、急なガレ場(岩場)が登場します。
ここが登山としての核心部で、一番大変な場所です。ここさえのぼりきれば後はラクなので、ゆっくりと攻略しましょう。
ルート取りは適当でも大丈夫ですが、なるべく矢印に従うと歩きやすくなるのでおすすめです。
稜線は絶景
さきほどの急登が終われば、稜線歩きです。
阿蘇山は樹木がなく暑いのですが、稜線からは風が出てくるので寒くなります。ハードシェルなどの防風装備を持っておくと良いです。



私は稜線で着ました
仙酔峡ルート
稜線からは、仙酔峡ルートがよく見えました。
奥に見えるのが駐車場なので、急登なのがわかりますね。みなさん、結構苦戦してのぼっているように見えました。
ヘリがうるさい
遊覧飛行のヘリがしょっちゅう飛んでいました。
このヘリは火口見学を目的としており、何台もビュンビュン飛んできます。非常にうるさいです。
阿蘇山は素晴らしい火山でしたが、ここが本当に残念なポイントでした。



後日、事故起こしてるし
観光するにしても、登山をするにしても、頻度が多すぎてうるさいとおもいます。ここはもう、登山する場所ではなく、観光地なのでしょう。残念。
無事に登頂


無事に登頂しました。
なだらかな稜線上のピークなので、景色はあまり変わりません。高岳自体はひとが多いですが、周りには休憩できる場所がたくさんあるので、私はその先まで少し歩いて休みました。
雨風さえ気を付ければ、登山装備も簡易的で問題ないです。トレランもしやすそうでした。
阿蘇山のライブカメラ


阿蘇山周辺のライブカメラの映像です。
阿蘇山は火山活動が活発な山域ですので、登山をする際はこれらの情報を上手に活用して、安全に楽しみましょう。
草千里ヶ浜のライブ映像がリアルタイムで見られます。
阿蘇山は初心者でも簡単


今回は、阿蘇山の登山について解説しました。
阿蘇山の最高峰は"高岳"です。登山をするなら、ここを目指しましょう。
樹木がなくて風がないときは暑いです。半面、稜線は風があると寒くなるので防風対策はしておきましょう。日焼け止めは必須。
登山道はどちらも見晴らしがよく、体力さえあれば、初心者でもぼりやすい山です。
ここまでダイナミックな火山は、日本中見渡しても阿蘇山くらいなものなので、みなさんもぜひ登山を楽しんでみてください。

